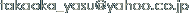介護福祉師
第一章:孤独
4.暗闇の中
4-7
翌日正午ごろ太陽の光がまぶしく目を覚ました。体が鉛のように重い。起き上がろうとすると、体中に激痛が走った。よく見ると足や腕のあちこちを擦り傷が出来ていた。痛みをこらえ、なんとかベッドより起き上がる。
「何やっているんだ・・俺」
目を閉じると、前日の出来事が走馬灯のように頭の中を駆け巡る。体中の傷や激痛が、前日の出来事の過酷さを物語っていた。
「生きているんだ。おれ。」
手を見ながら、小さく呟いた。昨日死ぬつもりでこの部屋を出て行ったはずなのに。
「死ねなかったな。」
大きくため息をついた。
体中の痛みに耐えながら、ゆっくりと立ち上がった。足を引きずるようにして歩きだす。
ドアノブに手をかけドアを開け部屋の外に出た。
太陽が出ている間に部屋の外に出るのは、約1年ぶりだった。階段の手すりにつかまり、ゆっくりと下りる。突き当りにある風呂場に入り、シャワーを浴びた。
もうひきこもり、すべてから逃げ出すのはやめにしよう・・・。
シャワーを浴び終え、ドライヤーで髪の毛を整える。髭を剃り、一番いい服を、鏡の前で確かめながら着た。
服を着替え終わると、鏡の中の自分をジーと見つめた。1年間も太陽の光を浴びていないためか色が白く、頬はコケ、目の下にはクマが出来、病人のように見える。そのうえ髪の毛は、肩につくほどに伸びている。
これでは誰も近づいてきてくれない・・・。
まず床屋に行き、このうざったい髪の毛を切ることにした。
玄関で靴をはき、玄関の扉を開けた。すると太陽の光とともに、冷たい空気が私の全身を包み込んだ。久しぶりにこういう感覚を味わう。その雰囲気にしばし呆然となった。周りの風景がまぶしい。
外に出ることをあれほど恐れていたのに、外に出ると不安や恐怖心といった感情がすっと胸の奥に消えて行った。
ゆっくりと床屋に向かった。
他人と逢うことが恐怖に感じる私は、床屋の前まで来たのはいいが、なかなかドアを開けることが出来ず、5回ほど行ったり来たりを繰り返したが、帰ればひきこもりに逆戻りだと覚悟をきめ、床屋のドアを開けた。
店内には客が誰もおらず、部屋の奥で主人らしき人が、椅子に腰掛け煙草を吸っていた。
「いらっしゃい。」
私に気づくと煙草の火を消し、こちらによって来た。主人は私の伸びきった髪の毛、色白な顔、何よりも、全体から滲み出る不健康そうな感じに少し戸惑っているような感じだったが、すぐに椅子へと案内してくれた。
「この長い髪の毛をバッサリ切ってください。」
そういうと、主人は無言で私の髪の毛を切り始めた。