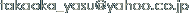介護福祉師
第一章:孤独
1.引きこもり
1-4
部屋から外に一歩も出ないと言ったが、私でも部屋から外に出ることが出来る時間がある。それは深夜。
両親も寝静まり、外に出ても他の人に会う可能性が限りなく低いこの時間帯になると、私は外に出ることが出来るようになる。
周りが静かになり人の気配がなくなると、音をたてないように部屋のドアをあけ、廊下をゆっくりと歩く。階段を忍び足でおり、まず台所に向かう。
電気もつけず、暗闇の中を手さぐりで冷蔵庫を探し当て、そのドアを開ける。
冷蔵庫の前に座り、中に入っている食べ物を根こそぎ食べる。食パンから始まりきゅうりやトマトなどの野菜、刺身などを手でつかみ口の中に放り込む。口いっぱいに放り込んだ後は、ろくに咀嚼もせずに牛乳で胃の中に流し込む。
味など関係ない。一日中部屋に引きこもり、水も飲んでいない状態だから、とにかくのどが渇く。パックの牛乳を一気飲みする。ものすごい勢いで口の中に放り込むため、時折のどに詰まり、呼吸困難に陥り、激しくむせこむ。咳が治まるとまた食べ物を口の中に放り込む。食べ物が終わりそうになると、横にある棚を物色し始める。その中にはせんべいやお菓子などが入っている。電気もつけず、暗闇の中で手を伸ばし、指先で何かを判断する。スナック菓子を開け、手のひらで掴み口の中に詰め込む。そしてこれも牛乳で胃の中に流し込む。
しかし食べるのも終盤に差し掛かると、突然の吐き気を感じトイレに駆け込む。そして胃の奥から突き上げてくる激しい感覚に耐えることができず、嗚咽とともにトイレに向かって、今食べた物を一気に残らず吐き出してしまう。全部吐いても不快感は治まることはない。トイレに向かい、何度も何度も空の嗚咽を繰り返す。力尽きトイレの便器にうつぶせに倒れこむ頃には、先ほど食べた物が体中から消え失せている。
夜になると、このように食べては吐くことを繰り返す。食べても必ず吐いてしまうことは自分でもよく分かっている。しかし私は食べて吐くことをやめることが出来ない。どうしても。
吐き気が治まると玄関で靴をはき、外に出ていく。家の近くにあるコンビニに向かうためだ。真夜中で、すぐ近くのコンビニに着くまでに、他の人に会う可能性はかなり低い。煌々と蛍光灯が点いているコンビニの中に入り、まずは酒を売っているところに向かう。焼酎やウイスキー、バーボンといった安くてアルコール度数の高いものを手に取る。酒の味なんかどうでもいい。今の自分を少しでも忘れたい。
レジでたばこを買い、店員と目を合わさないようにし、お金を払いコンビニを後にする。そして静かに玄関の戸をあけ家の中に入り、忍び足で階段を上がり自分の部屋の中に入る。ベッドに座り、先ほど買ったウイスキーをコップに、そのまま並々と注ぐ。水や氷で割ったりはしない。ストレートで口の中に流し込む。飲み込むと食道や胃が焼けるように熱い。歯を食いしばりその感覚に耐える。1杯目で酔うことは絶対にない。すぐに2杯目をコップに注ぐ。そしてそれもほとんど一気に胃の中に流し込む。
夜中、独りで部屋の中にいると、どうにかなりそうになる。その感情を酒を飲むことによってかわしている状態だった。煙草をくわえ静かに息を吐き出した。しばらくすると酒が体を回り始め、頭がクラクラしてくる。眩暈もしてくるがそれでもコップに酒を注ぐ。
最後は目の焦点が次第に合わなくなり、意識が遠くなるようにベッドに横になる。
私はこのようにしないと眠ることが出来ない。
深夜動き出し、朝日が昇る頃横になり夕方近くになると目を覚ます。生活リズムは完全に昼夜逆転になっていた。夕方目を覚ますと、二日酔いのため頭の芯がズキズキと痛み、体中を倦怠感が覆い尽くす。
目を覚ますのが辛い。胸が不安で押しつぶされそうになる。頭をおさえながら考える。私はどうなってしまうのだろう。