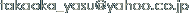介護福祉師
第一章:孤独
2.回想
2-1
私は一人っ子でした。家族は父、母、私の3人暮らし。裕福ではありませんでしたが決して貧しいとはいえない、ごくありふれた中流家庭でした。両親も仲がよく、そして私に愛情を注いでくれました。
一人っ子ということで、私は両親に可愛がられ何一つ不自由なく過ごしました。欲しいものは何でも買ってもらい、怒られたという記憶がありません。考えてみると甘やかされて育ったのかもしれません。
ただひとつ不満があるといえば、小学校の頃から両親が共働きで、学校から帰っても家には誰もいませんでした。家に帰ってから両親の帰りを待つ時間、その時間は私にとってとても寂しく、怖く、そして長く感じられました。夕御飯の時間になっても両親が帰宅することはごく稀で、母親が朝作ってくれた冷蔵庫から取り出し、電子レンジで温めて独りテレビを見ながら食べました。独りで食べるご飯は味気なく、美味しくなかったのですが、せっかく母が作ってくれたものだからと全部残らず食べました。ご飯を食べたあと食器を洗いながら母の帰りを待ちました。母はいつも食器を洗い終わる頃必ず家に帰ってきました。
母が帰ってくると急いで玄関まで走っていってドアを開け、笑顔で母を迎えました。ドアの向こうに母が立っているのを見るのがとても嬉しく、そしてほっとしたものでした。
成績も両親に心配をかけたくないと頑張って勉強したため、常にクラスで中から上位あたりを保っていました。担任の先生、私、母親の3人で行う三者面談の時、先生から何の問題のない生徒だと言われ、誇らしかったことを今でも覚えています。小学校の私はその辺にいるような、ごく普通の子供でした。
両親が共働きのため、学校の行事が憂鬱でした。仕事の都合上、運動会や参観日、音楽会などに来てもらったという記憶がありません。運動会の時、周りの友人が家族でお弁当を広げ、楽しそうに会話しながら食べている横で、私はコンビニのおにぎりを一人淋しく食べたものです。運動会中、友人は家族の前で張りきり、楽しそうにかけっこなどの競技を行っていましたが、私には見てもらう家族が誰一人いないため、何か力が入らず、そしてもう一つ楽しむことができませんでした。
仕方がないと自分には言い聞かせてみるものの、楽しそうにしている友人がなんともうらやましく思えたものでした。
そして一人っ子ということもあるかもしれませんが、私は友人と楽しく運動をしたり、遊んだりすることを好みませんでした。友人から誘われたら遊んだりしましたが、自分から誘うことはほとんどなく、一人を好みました。
学校が終わると独りで誰もいない家に帰り、テレビゲームをして時間をつぶしました。テレビゲームは退屈と孤独を忘れさせてくれる、いい道具になりました。両親は一人っ子の私を不憫に思ったからでしょうか、私の欲しがるゲームを何でも買ってくれました。そのため、私はゲームに飽きるとすぐ違うゲームをすることができ、ゲームに飽きることはほとんどありませんでした。独りで家にいても退屈をしないほどに。特に私は飛行機に乗り敵を次々に壊していくゲームが好きでした。物を壊していくと心の中にあるもやもやが、少しだけ晴れたような気がするのです。不思議でしたが、物を壊していくゲームを時間が過ぎるのを忘れるほど熱中したものでした。