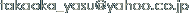介護福祉師
第一章:孤独
3.秋
3-3
秋が深まる頃、私は死を意識するようになりました。
このままの状態がずっと続き、立ち直ることなどできないのではないか。自分の中に希望という文字が存在しない。親にこれ以上迷惑をかけるわけにはいかない。自分ではどうしたらいいのかわからない。
苦しくて、苦しくて明日なんて考えられない。この苦痛、恐怖から解放されたい。
死という言葉が持つ独特の世界に魅力を感じた。私を落ち着かせ、安心させてくれる唯一の言葉のように思えるのです。
私はもう死んだほうがいいのではないか。その言葉が私の頭の中を何度も駆け巡った。
深夜両親が寝静まると、一人起きて父の車を借り、何時間も車で山の中をうろうろするようになった。死に場所を探すのが目的だった。
決して誰も足を踏み入れることのないようなところを探した。
気がつくと季節は12月の中旬に差し掛かっていた。山の奥のほうに行くと積雪が見られ、人の気配はほとんど感じられない。
試しに山奥の雪に埋もれた場所で、車から降りてみる。半径1キロ以内に民家どころか電灯もないような場所で、辺り一面闇に覆われ、1メートル先も見えない。風は凍てつき突き刺さるように吹きつけてくる。
しかし、私はその中で凍えながらも、なぜか気持が落ち着いてくるのを感じた。ここならば誰にも見つかることはなく、静かに死ぬことが出来るのではないか。そこにいるとなぜか、昔からこの場所が私を待っていたような錯覚に陥った。
1週間ほど他の場所を探してはみましたが、ここ以上の場所を発見することが出来ず、ここを死に場所と決めた。通ってきた道が舗装されていない砂利道で、車通りは全くない。人に会う可能性はゼロに近いと予想できる。
帰り道、近所にあるホームセンターで丈夫そうな縄を買い、部屋に戻った。
部屋に戻り、独り買ってきた縄を見つめながら考える。
これから私は死ぬのだと。心の中は驚くほど落ち着いていた。死への不安や抵抗もなく、ただ、死を受け入れる。死は私を救ってくれるものだと、心の中で何度も唱えた。もう思い残すことはない。生きていても迷惑をかけるだけだし、社会で生きていける自信がない。
次の日の夜。両親が寝静まったのを確認すると、縄を持ち部屋を出て車に乗り込んだ。もうこの家には、戻ってこないと決意して。